競馬予想でよく耳にする「スローペース」や「ハイペース」という言葉。なんとなく聞いているけれど、具体的にどういうこと?予想にどう役立つの?そう感じている競馬ファンは多いのではないでしょうか。
実は、レースの「ペース」は、馬の能力や適性を引き出す上で非常に重要な要素であり、予想の精度を大きく左右します。ペースを読めるようになれば、あなたの競馬予想は格段にレベルアップするはずです。
この記事では、競馬初心者の方でもレースのペースを簡単に見極め、予想に活かせるよう、以下のポイントを徹底的に解説します。
- スローペースとハイペースとは何か?
- それぞれのペースが馬の能力やレース結果にどう影響するか?
- 実戦で役立つ!ペースの見方と予想への活用法
この記事を読み終える頃には、あなたはレース映像が今までとは全く違って見えるようになり、より深い洞察力で勝ち馬を見つけられるようになるでしょう。
競馬の「ペース」とは?スローペースとハイペースの基本
競馬における「ペース」とは、レース全体の流れや、各区間での速さのことを指します。大きく分けて「スローペース」「ハイペース」「ミドルペース」の3種類があります。
1. スローペース:瞬発力勝負になりやすい
スローペースとは、レース序盤から中盤にかけての競走ペースが全体的に遅く、馬群が凝縮しやすい流れのことです。特に、最初のコーナーまでの先行争いが緩やかだったり、逃げ馬が無理なく自分のペースで走れたりする場合に起こりやすいです。
特徴:
- スタミナ消耗が少ない:全体的にスピードを抑えて走るため、馬のスタミナ消耗が少なくなります。
- 末脚の切れ味が重要:最後の直線に入ってから一斉に加速する展開になりやすく、強烈な瞬発力を持つ馬が有利になります。
- 前残りの可能性:先行馬や逃げ馬が余力を残しやすい傾向にあるため、そのまま粘り込んでしまう「前残り」が決まりやすくなります。
例:コントレイルの皐月賞(2020年)
三冠馬コントレイルが勝利した2020年の皐月賞は、序盤のペースが比較的落ち着き、コントレイルが好位から末脚を伸ばして勝利しました。これは瞬発力が問われるスローペースの恩恵を受けた一例と言えるでしょう。
2. ハイペース:スタミナと持続力勝負になりやすい
ハイペースとは、レース序盤から中盤にかけての競走ペースが全体的に速く、先行争いが激しくなったり、逃げ馬がオーバーペースで飛ばしたりする流れのことです。
特徴:
- スタミナ消耗が激しい:全体的に速いスピードで走るため、馬のスタミナ消耗が激しくなります。
- 持続力と底力が重要:スピードだけでなく、長い距離や速いペースを持続できるスタミナや底力が問われます。
- 差し・追込が決まりやすい:先行馬がバテて失速しやすいため、後方から追い込んでくる差し馬や追込馬が有利になります。「差し馬総崩れ」といった表現も使われます。
例:イクイノックスの天皇賞(秋)(2023年)
G1を連勝中のイクイノックスが圧勝した2023年の天皇賞(秋)は、スタートから速いペースで流れ、最終的に強いスタミナと持続力を持つイクイノックスが他馬を寄せ付けませんでした。これはハイペースが先行馬に厳しい展開となり、後方から脚を伸ばした馬が有利になった典型的な例です。
3. ミドルペース:バランスの取れた総合力勝負
ミドルペースとは、スローペースとハイペースの中間のペースで、極端な展開になりにくい流れのことです。馬のスピード、スタミナ、瞬発力、レースセンスといった総合的な能力がバランス良く問われるため、最も実力が反映されやすいペースと言えます。
特徴:
- 総合力が問われる:どの脚質の馬にもチャンスがあり、バランスの取れた能力を持つ馬が好走します。
- 予想が難しい場合も:展開の読みが難しくなることもありますが、実力馬が力を発揮しやすい傾向にあります。
ペースが馬の能力とレース結果にどう影響するか
レースのペースが、競走馬の能力やレース結果にどのような影響を与えるのか、具体的な例を交えながら見ていきましょう。
瞬発力に優れた馬の場合
瞬発力に優れた馬は、スローペースからの瞬発力勝負に非常に強いです。道中ゆったりと脚を溜め、最後の直線で一気にギアを上げることで、持ち味を最大限に活かせます。
得意なペース:スローペース
苦手なペース:ハイペース(序盤から消耗するため、最後の瞬発力が削がれる)
例:ディープインパクト
歴代最強馬の一頭であるディープインパクトは、まさに瞬発力の塊のような馬でした。道中ゆったりと進み、最後の直線で「飛ぶような」末脚を繰り出す姿は、スローペースからの瞬発力勝負において無類の強さを誇りました。
スタミナと持続力に優れた馬の場合
スタミナと持続力に優れた馬は、ハイペースからの消耗戦に強いです。序盤からペースが速くてもバテずに追走し、粘り強く脚を使い続けることができます。上がりがかかるタフなレースで真価を発揮します。
得意なペース:ハイペース
苦手なペース:スローペース(瞬発力勝負になると、切れ負けする)
例:ゴールドアクター(有馬記念2015年)
スクリーンヒーロー産駒のゴールドアクターが勝利した2015年の有馬記念は、道中から比較的速いペースで流れました。ゴールドアクターは中団から早めに進出し、そのまま押し切って勝利。これは、ハイペースのタフな展開を味方につけた勝利と言えるでしょう。手綱を取った吉田隼人騎手も、そのスタミナを最大限に引き出しました。
先行力のある馬の場合
先行力のある馬は、前に位置取り、自分のペースでレースを進めたいタイプです。スローペースであれば、そのまま押し切る「前残り」を狙えます。しかし、ハイペースになると、序盤から消耗してしまい、最後は失速してしまうリスクが高まります。
得意なペース:スローペース
苦手なペース:ハイペース(競り合いになると厳しい)
例:パンサラッサ
逃げ戦法で数々のG1を制したパンサラッサは、まさしく先行力とスピードを活かすタイプです。ドバイターフや天皇賞(秋)など、自身のペースで逃げ切ることで持ち味を最大限に発揮しました。騎乗する吉田豊騎手も、巧みなペース配分で馬の能力を引き出しています。
追込馬の場合
追込馬は、レース序盤は後方で待機し、最後の直線で一気に追い込んでくるタイプです。ハイペースで先行馬がバテる展開になれば、差し切りが決まりやすくなります。しかし、スローペースで前が止まらない展開になると、届かずに終わってしまうことが多いです。
得意なペース:ハイペース
苦手なペース:スローペース(前が止まらないため、届かない)
例:ブエナビスタ
多くのG1で好走したブエナビスタは、牝馬ながら強烈な末脚が持ち味の追込馬でした。特に直線が長いコースや、ハイペースで先行馬が消耗する展開になれば、最後方からごぼう抜きするシーンを何度も見せてくれました。池添謙一騎手とのコンビで、ファンを魅了しました。
実戦で役立つ!ペースの見方と予想への活用法
では、実際にレースのペースをどのように見極め、予想に活かせば良いのでしょうか?
1. 過去のレースラップを確認する
最も客観的にペースを判断できるのが、過去のレースラップ(各区間のタイム)を確認することです。JRAの公式サイトや競馬新聞、データサイトなどで確認できます。
- 前半と後半のラップタイムを比較:全体的に前半のラップが速ければハイペース、遅ければスローペースの傾向にあります。
- 1ハロン(約200m)ごとのラップタイムの変化:特にラスト3ハロン(600m)のラップが速くなっていれば瞬発力勝負、最後まで落ちていなければ持続力勝負の傾向です。
具体的な見方:
例えば、芝2000mのレースで、最初の1000mが58秒台と速く、後半1000mが60秒台にかかっているようなら「ハイペース」。逆に最初の1000mが60秒台と遅く、後半1000mが58秒台のようなら「スローペース」と判断できます。
2. 出走馬の脚質を把握する
出走馬全体の脚質(逃げ、先行、差し、追込)を把握することも重要です。逃げ馬が複数いたり、先行したい馬が多い場合は、先行争いが激しくなりハイペースになりやすい傾向があります。逆に、逃げ・先行馬が少ない場合は、スローペースになりやすいです。
例:
もし、タイトルホルダーのような生粋の逃げ馬が複数出走しているレースであれば、序盤から激しい先行争いが予想され、ハイペースになる可能性が高まります。
3. 騎手のコメントや作戦に注目する
レース前の騎手や調教師のコメントに注目しましょう。「今回は前に行きたい」「控える競馬を試す」など、レース展開のヒントになる発言がある場合があります。また、有力馬の騎手がどのような作戦を考えているかも、ペースを占う上で重要です。
例:
栗東の杉山晴紀厩舎に所属するスターズオンアースが、ルメール騎手で出走するとして、騎手が「今回はじっくりと脚を溜めたい」とコメントしていれば、後方からの差しを狙う可能性が高く、その馬にとってはスローペースが理想的だと推測できます。
4. 馬場状態やコース形態を考慮する
馬場が重い場合はスピードが出にくいため、全体的にペースが遅くなる傾向があります。また、坂のあるコースや小回りコースでは、スタミナ消耗が激しくなるため、相対的にハイペースになりやすい傾向があります。
まとめ:ペースを制する者が競馬を制す!
この記事では、競馬の「スローペース」と「ハイペース」の基本的な見方から、それぞれのペースが馬の能力やレース結果にどう影響するか、そして予想への活用法までを解説してきました。
競馬予想において、馬の能力や調子、血統といった要素はもちろん重要ですが、レースの「ペース」という視点を取り入れることで、あなたの予想は飛躍的に向上します。
- スローペースは瞬発力勝負、ハイペースはスタミナと持続力勝負になりやすい。
- 馬の脚質や適性によって、得意なペースと苦手なペースがある。
- 過去のレースラップ、出走馬の脚質、騎手のコメント、馬場状態やコース形態など、多角的な視点でペースを分析する。
これらの知識を武器に、ぜひ次回の競馬予想から「ペース読み」を意識してみてください。レースの流れを正確に把握することで、どの馬がそのレース展開に最も適しているかが見えてくるはずです。そして、あなたの読みが的中し、勝ち馬を導き出した時の喜びは、何物にも代えがたいものとなるでしょう。
さあ、今日からあなたも「ペース読みマスター」への道を歩み始めましょう!

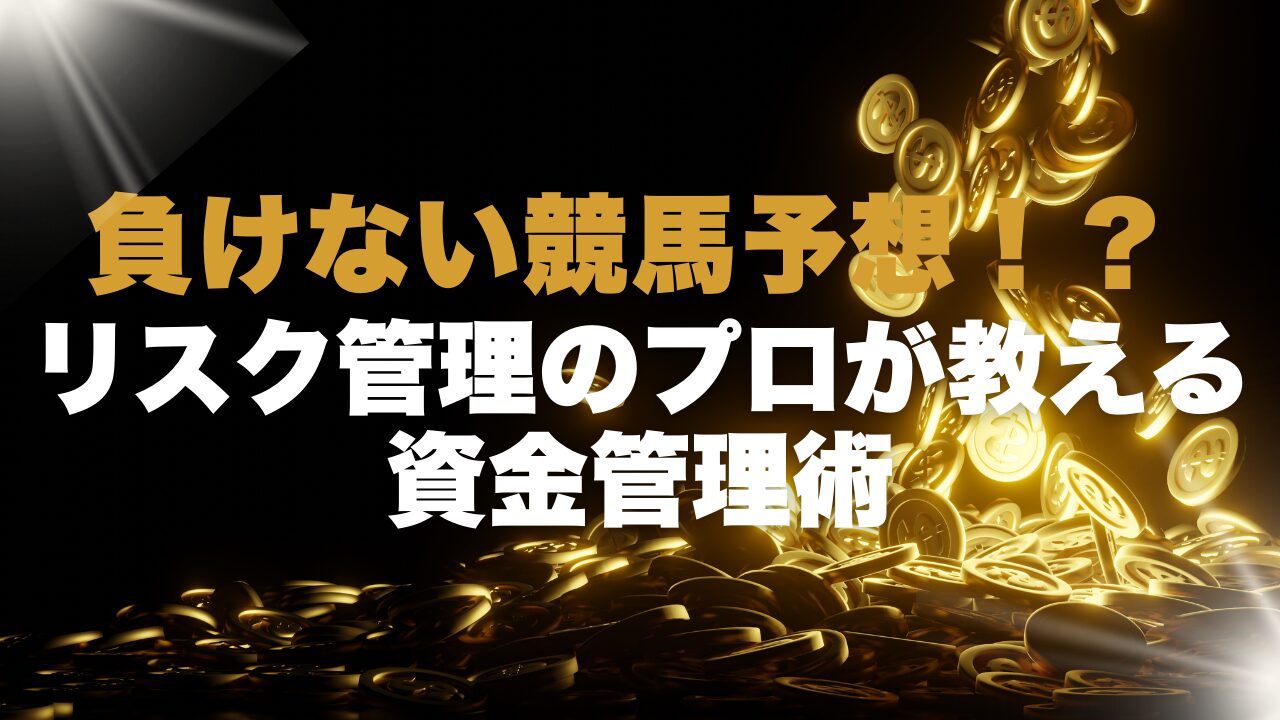

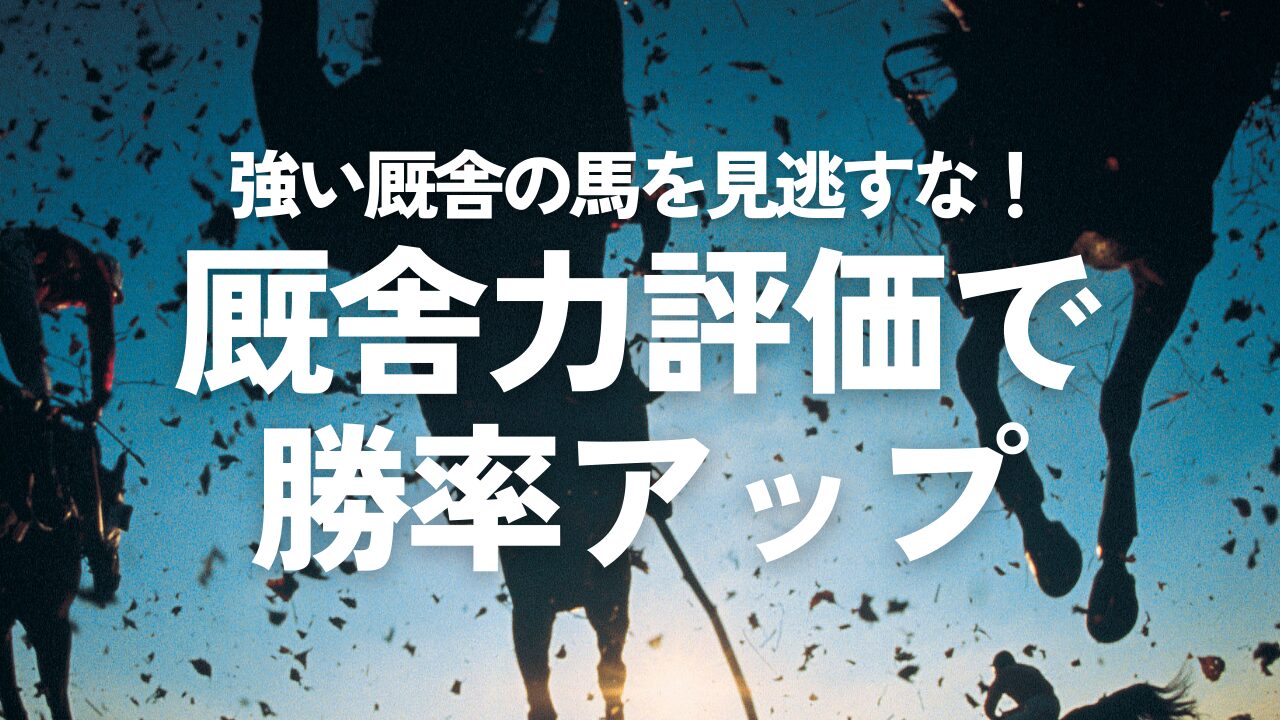
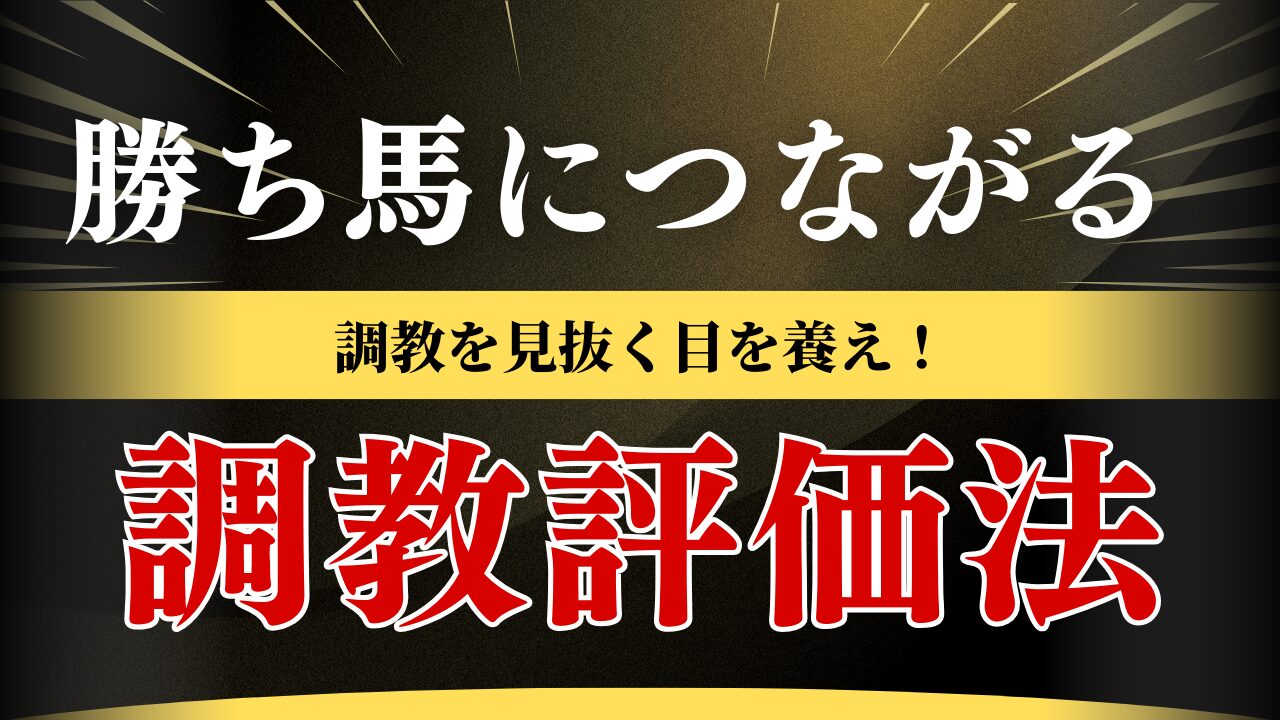



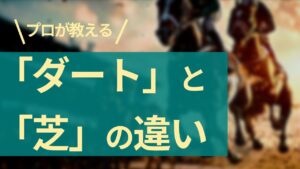
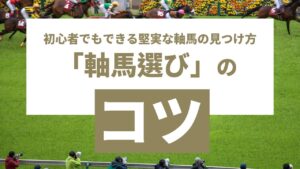

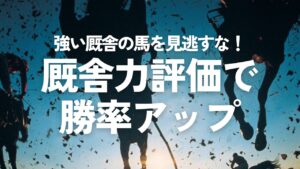



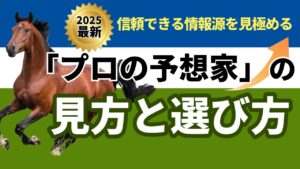
感想や学んだことをコメントして予想力を上げよう!